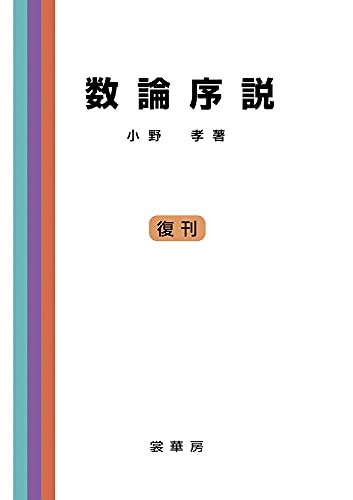昨日は、オイラーの素数生成多項式に関して「私の発見」を紹介させていただきました。
tsujimotter.hatenablog.com
執筆時は、この研究の先行研究にあたるものを発見できず、「先行研究はあるかわからないが独自にこんな発見をした」というスタンスを取っていました。しかしながら、やはり探せばあるものです。
このブログでも何度かお世話になっている木村巌先生より、2件ほど教えていただきました。私自身の力で見つけることができなかったので、大変ありがたいお話です!
[1]
On a lower bound for the class number of an imaginary quadratic field[2]
An inequality between class numbers and Ono's numbers associated to imaginary quadratic fields
この様子だと他にも類似の研究はありそうです。勉強になります。
もちろん、私の記事と完全に同じ結果というわけではありません。私の記事と先行研究 [1][2] の違いをまとめると、次のようになります。
- tsujimotter:
の範囲において
が素数を生成する確率に着目
- 先行研究[1][2]:
の範囲において
の素因数の個数(特に
の範囲で個数が最大のもの)に着目
実は素因数の個数に着目すると、後半で示すように非常に明快な関係が得られるのです。この辺は問題の定式化のセンスを感じますね。私には思いつかないアイデアでした。
というわけで、この分野の考え方に親しむためにも、特に先行研究の考え方と結果についてまとめてみたいと思います。
tsujimotter.hatenablog.com
オイラーの素数生成多項式のメカニズム
ここでは、オイラーの素数生成多項式 が
に対して合成数の値を返すとき、対応する類数が
より大きくなる仕組みについて、そのメカニズムを述べたいと思います。
虚2次体を とします。ここで、
は平方因子を持たない整数で、
です。
の整数環(最小多項式の係数が有理整数であるような
の元全体)を
と書くと、
と表せます。ここで
となります。このように、整数環が によって場合分けされるのが2次体の難しいところです。
また、 の判別式を同様の場合分けにより
とします。
このとき、 を有理整数として、
という整数に着目します。この数のノルムを計算すると
となります。
ここで、多項式 を定義すると、
においては、まさにオイラーの素数生成多項式
そのものになっていますね。
次にこの多項式(すなわち、 のノルム)とイデアル類群の関係について考えていきましょう。
まず、イデアルの標準的な表現方法について説明します(これがもっとも重要です)。
のイデアルとは、
の部分集合
であって、①加法に対して群をなし、②
倍で閉じているものをいいます(こういう集合を
-加群という)。特に加法群であることに着目します。
このとき、2次体のイデアル は階数
の自由
-加群であることが示されます。このことから、
の自由
-加群としての基底を
とし、
を次のような記号によって表すことにします:
また、 の原始的イデアルとは、
より大きい有理整数によって割り切ることができない
のイデアルのことです。ここで、
の任意の原始的イデアルを
とすると、有理整数
を用いて、
の
-基底は
と表すことができます。すなわち
ということです。これはイデアルの形を非常に限定的にしますね。また、上の形から と取ることができ、
の元を
に足し合わせることによって、
を
の範囲に限定することができます。このような
の取り方は一意的です。
したがって、 の任意の原始的イデアル
は、有理整数
を用いて
と一意的に表すことができます。これを の標準基底による表示と言います。
今は、原始的イデアル が与えられたとき、
と表されることについて述べました。逆に、イデアルとは限らない集合
が与えられたとき、これがイデアルであるための必要十分条件が存在します。
この右辺がまさに素数生成多項式 になっていますね。すなわち、素数生成多項式の値
の約数が
であるという条件は、
が
のイデアルであることと同値だったわけです。
ここで、いよいよ のイデアル類群を考えます。
のイデアル類群とは、
の分数イデアル全体のなす群を
として、
を
の単項分数イデアル全体のなす群
で割って得られる群
のことです。 の位数を
の類数といい、
と表すことにします。
ここで、イデアル類群の各類に、いったいどんなイデアルが属するのかが分かればイデアル類群を掌握することができます。重要なのは、各類には次のような条件を持つイデアルが存在します。
は、虚2次体のとき
となるような上限値です。
したがって、 であるような
の約数
全体を考えれば、類が重複することはありえますが、イデアル類群の類をすべて列挙することができるようになります。
また、 であるので、
としては
の範囲だけ考えれば十分ですね。そういうわけで、多項式
の非常に限定的な範囲における値
の約数を調べれば、その値によってイデアル類群の類がすべて列挙されるということになります。これが素数生成多項式とイデアル類群の関係になります。
が素数になるときは、明らかに
を超えてしまいますので、新しいイデアル類を生成するためには
が合成数になる必要があります。いわば、合成数
がイデアル類群を生成する ということですね。大変面白いです!
先行研究 [1][2] の結果
以上の話を前提とした上で、先行研究 [1][2] の結果について概略を述べましょう。特に、[1]の話を中心にまとめます。
[1] では多項式 を
で考え、その中での
の(重複を含む)素因数の個数の最大となるときの個数を
としています。すなわち、自然数
の重複を含む素因数の個数を
とすると(たとえば、
とすると、
です)
となります。
これを用いると、実は次のきわめて綺麗な不等式が得られます。
これは非常に面白いですね!!
Theorem 1を用いると、 は明らかです。したがって、その逆
を示すことができれば、次の定理が得られます。
ということは、
の素因数の個数がすべて1つ、つまりすべて素数ということです。これこそが、Rabinovitch (1913) の定理ですね!
さらには、 を示すことで、次が得られるというのが参考文献 [1] の結果というわけですね。
Theorem 2の証明は少し面倒なので、ここでは簡単な議論で示せるTheorem 1を証明してみたいと思います。次のLemma 1を認めます。
(1) のとき、
(2) が単項イデアルならば
または
(2) は特に面白くて、対偶を取ることで、特定の条件を満たすイデアルが単項ではないことが判定できます。
これをつかってTheorem 1を証明します。
(Proof of Theorem 1)
の範囲で
の素因数の個数が最大のものを考えて、これを
とする(すなわち、
)。
このとき、 は重複を許して
と素因数分解される。ここで
とおく。 より、
はすべてイデアル。
ここで、 個のイデアル類
は、 の中ですべて相異なるイデアルである。これは以下の理由による。
に対して
なるイデアル類を考える。すると
であるが、Lemma 1の (1) より
であるが、 より
であり、Lemma 1 の (2) の対偶を使うと は単項イデアルではない。したがって、
である。
以上により、 が示された。
ここまでが先行研究 [1] の結果です。先行研究 [2] について手短に述べます。
[1] のきっかけとなった小野孝先生 *1 により、類数を上から押さえる不等式
が予想されています。実際はこの予想は不成立で、無限に多くの において上記の不等式が成立しない例を作れるそうです。
これに対して、[2] では予想の修正を行っています。 を虚2次体
で完全分解する最小の素数とすると
が成り立つという定理を示しています。特に判別式が のケースにおいては、
は
で完全分解するので、
となり小野孝先生の予想が成り立つということだそうです。
tsujimotterの実験結果との比較
こんな風に、先行研究 [1][2] によって、素数生成多項式と類数の関係が明快に表せたわけですが、これによって私の実験結果を説明することはできるでしょうか?
私の方は素数生成確率 を扱っていて、[1][2] の方は素因数の個数の最大値
を扱っています。残念ながら、これらの量を明確に結びつけるのは非常に難しいです。
雑な議論でよければ、これらの関係を雰囲気でよければ結びつけることはできます。論理的に正しくないということを前置きした上で、少しだけ議論を展開してみましょう。
素因数の個数の最大値 が、素数生成確率の逆数に比例するという大胆な仮定をおきましょう。すなわち、素因数の個数の最大値が大きい(resp. 小さい)ということは、素数になりづらい(resp. なりやすい)ということです。式にすると
ということですね。
また、Theorem 1より ですから、逆数をとると
ということになりますね。したがって、私の実験で得られたものに近い下界 が得られました。
もちろん、この議論は全く正しい議論ではないわけですが、おおよそ前回の結果が説明できた気分になれます。
小野孝先生による不等式(一般には不成立ですが)
を用いると、両辺 log をとって
となり、上界らしき不等式が得られます。
グラフに載せてみると、だいたい とすると、ちょうど良さそうな上界と下界となります。