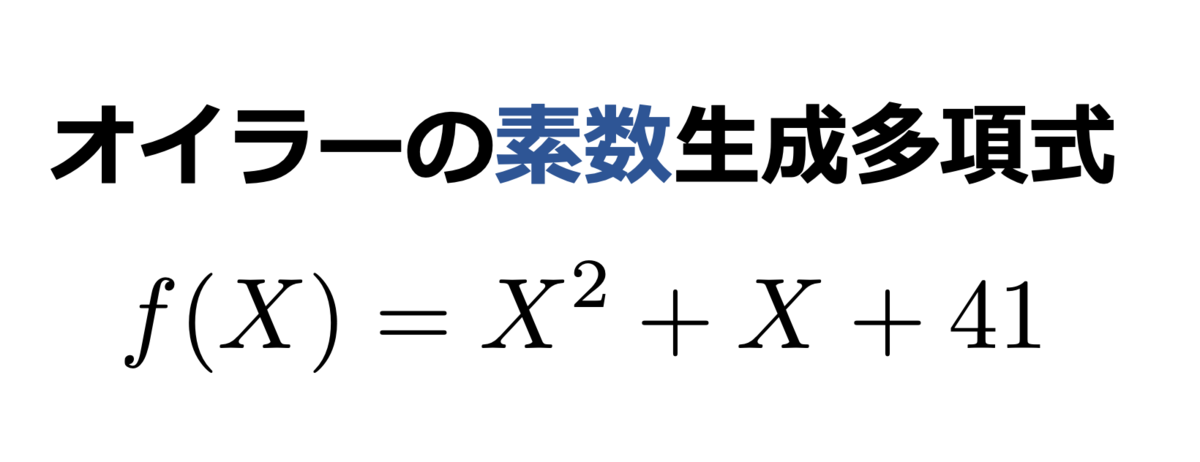最近、「リーマン面」の勉強が「微分形式」の章に差し掛かりました。接ベクトル空間という線形空間や、その双対空間が出てきてまさに線形代数になっています。そんなわけで線形代数の復習として、以下の事実を示したいと思います。
斎藤毅先生の「線形代数の世界」の命題2.13から。
このとき、線形写像 で、
を満たすものがただ一つ存在する。
まずは、主張の確認をしていこうと思います。 は線形空間なので、基底というベクトルの組
がとれます。これによって、任意のベクトル
は
のように一意的に表せるわけですね。
さて、 から
への線形写像というのは、任意の
の元
に対してその値
が定められていて、かつ、線形性なる条件を満たしているものです。
というわけで、本当はすべての の元に対して値が定まっていなければいけない。
しかしながら、線形性から
が成り立ちますので、 は
というたった
個のベクトルに対してその行き先が決まっていれば、あとは自動的に決まってしまうのです。まさに 線形性のマジック という感じがします。
ここで気になるのは、基底の行き先として を予め与えたときに、対応する線形写像
は存在するのか、という問題です。存在すれば一意なので対応する線形写像が存在するかどうかが焦点となります。

もちろん、単に「写像」というだけであれば、行き先はいくらでも決められるので必ず存在します。一方で「線形写像」に限定したときに存在するかというのは明らかではありません。そのような線形写像が存在することを保証するのが命題2.13の主張なわけですね。単に存在するだけでなく、証明の中では対応する線形写像を実際に構成します。
主張の内容を思い切り勘違いしていましたので、記事公開後に修正しました。
元々は「線形写像は基底の行き先だけで決まる」という内容にしていたのですが、(もちろんそれも事実としては正しいのですが)命題2.13の主張としては「基底の行き先を任意に与えると、それに対応する線形写像が存在する」の方がポイントだったわけですね。
タイトルもミスリーディングなので変えます。
対応する線形写像が存在することの何が嬉しいのでしょうか。線形写像 から
への
-線形写像全体を具体的に考えるときに、この命題が助けになりそうです。実際、双対空間と呼ばれる「
から
への線形写像全体のなす
-線形空間」の基底を求めるのにこの命題を使うのですが、長くなりそうなのでまた別の機会に紹介したいと思います。